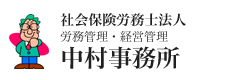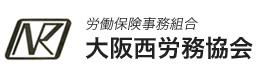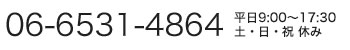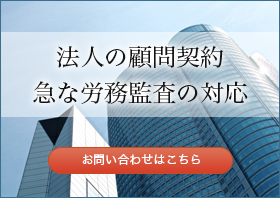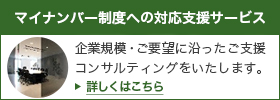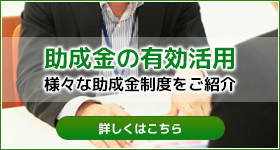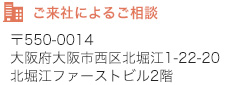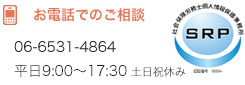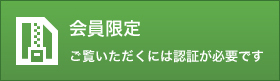試し通勤など段階を踏んだ復帰支援を 心の健康問題による休業者の職場復帰への対応
近年、経済・産業構造が変化するなかで、仕事や職業生活に対する強い不安やストレス、悩みを抱える労働者が増加しており、「職場における心の健康づくり」が課題となっています。
ここでは、心の健康問題により休業した労働者が円滑に職場復帰するための対応策について確認します。
職場における休業の現状
「令和6年版厚生労働白書」によると、仕事を原因とする精神障害により労災保険の請求が行われた件数は、2012年度からの10年間で約2.13倍に増加しています。
2022年度においては、精神障害の原因が仕事であると認定され、労災保険給付が行われた件数は710件となり、請求および認定件数ともに過去最多となりました。
原因は「パワーハラスメント」が147件と最も多く、次いで「悲惨な事故や災害の体験や目撃」、「仕事の内容や量の変化」となっています。
また、全国健康保険協会(協会けんぽ)によると、傷病手当金において精神障害等が占める割合は、1995年以降増加傾向で推移しており、2022年度における精神障害等の1件当たりの受給日数は35.06日となっています。
うつ病やパニック障害、適応障害などの精神障害をはじめ、ストレスや強い悩み、不安など心身の健康や社会生活を脅かす可能性のある精神及び行動上の問題(以下、メンタルヘルス不調)は、比較的長期間にわたる休業を余儀なくされる原因となることが報告されています。
職場復帰支援の必要性
職場におけるメンタルヘルス対策は、第一予防として「メンタルヘルス不調の未然防止」、第二予防として「メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応」、第三予防として「職場復帰支援」の、3つの柱から成り立っています。
職場復帰支援は、メンタルヘルス不調で休業した労働者が円滑に職場復帰し、業務の継続を可能とすることを目的としています。
事業主は、必要な関連規定の整備を行い、個々の事業場の実態に即した形で「職場復帰支援プログラム」を策定する必要があります。
このプログラムは、事業場全体のルールであり、休業開始から通常業務復帰までの標準的な手順、内容及び関係者の役割と連携方法を定め、プライバシー保護に十分に配慮していることを記載した上で、すべての労働者や管理監督者へ周知し、組織的かつ計画的に取り組むことが求められます。
また、心理的支援として、事業所において研修や情報提供を通じて職場復帰支援への理解を高め、職場復帰しやすい体制を作ることも重要となります。
職場復帰支援の流れ
厚生労働省が公開している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、職場復帰支援は休業の段階から復職、復職後のフォローアップまで、5つのステップを踏んで進めていくことが推奨されています。
第1ステップとして、労働者による休業診断書の提出を受けて、休業診断書の提出を受けて、休業の開始時や休業中に必要となるケアなど、本人の情報を関係者間で共有します。
ここでは労働者が安心して療養できるように、傷病手当金などの経済的保障や休業の最長保証期間といった、必要な事務手続きや職場復帰支援の手順を説明することが必要です。
第2ステップでは、休業中の労働者から職場復帰の意思表示を受けた段階で、主治医による職場復帰可能の判断が記された「復職診断書」の提出を求めます。ここでは、産業医など対して、職場の実態について社内制度や仕事内容などの情報提供を行った上で精査と意見を求め、働ける状態であることを確認することが重要です。
第3ステップは「職場復帰支援プラン」の作成です。
労働者の職場復帰に対する意思確認を行い、産業医などの医学的見地からの意見や、業務遂行能力も含めた労働者の状態、職場環境、労働者の今後の就業に関する考えなど、必要な情報を収集・評価し、職場復帰が可能かを判断します。
職場復帰支援プランには、個別の事情に即して、職場復帰予定日や就業上の配慮、人事労務管理上の対応、就業上のフォローアップなど具体的な支援内容を検討して記載する必要があります。
第4ステップでは、産業医の意見書などに基づいて、事業主が最終的な職場復帰の決定を行います。
休業中の労働者の状態を最終確認した上で、主治医に対して就業上の配慮の内容について情報を提供し連携を図ります。
処遇の変更等がある場合は、事前に就業規則などに定めておく必要があります。
職場復帰を経た後の第5ステップは、復帰後のフォローアップです。
管理監督者や同僚への過度な負担を回避するよう配慮した上で、職場環境の改善を図るとともに、必要に応じて職場復帰支援プランの評価や見直しを行います。
家族からの相談対応も含め、疾患の再発や新しい問題が発生していないかなど、いかに管理監督者や産業医などの関係者が情報を共有し、連携を図りながら支援を継続していくかが鍵となります。
試し(リハビリ)出勤制度
職場復帰支援においては、より早い段階で職場復帰の試みを開始し、労働者の職場復帰をスムーズに行うことを目的として、「試し(リハビリ)出勤制度」を社内制度として設けることも有益です。
運用については、制度の目的を明確にし、賃金や就業時間などの労働条件や人事労務管理上の位置づけを具体的に検討して、就業規則などに一定のルールを設けておくことが必要です。
具体的には、第3から第4ステップにかけて、通常の勤務時間と同じ時間帯に模擬的な軽作業などを行う「模擬出勤」や、通勤経路で移動を行い、一定時間を過ごして帰宅する「通勤訓練」、職場復帰の判断を目的として、試験的に一定期間継続して出勤する「試し出勤」の適用が挙げられます。
適用にあたっては、産業医などと連携してその必要性を検討し、主治医からも本人の療養の妨げにならないとの判断を受けることが重要です。
特に「試し出勤」においては、病気による休業期間中であることを鑑み、必要な時間帯、様態、時期、期間等に限り、長期にわたり適用することや業務指示を行うことは避けましょう。
「試し出勤」が労働時間として認識された場合、賃金支払義務が発生し、傷病手当金の受給に影響が及ぶ可能性があるため、注意が必要です。
また、職場復帰の基準は完全復帰ではない状態での受け入れが前提となります。
職場復帰後の労働負荷を軽減するために、短時間勤務への変更や残業・深夜労働の禁止、軽作業や定型業務への従事、出張制限、業務制限などの制度を採用し、段階的に元の勤務状態へと戻すことは、円滑な職場復帰を促す上で重要な対応策となります。
プライバシーの保護
職場復帰支援で扱う健康情報は、労働者のプライバシーに関わるものであり、個人情報の中でも厳格に保護する必要があります。
主治医や家族からの情報収集の際は、労働者が不信感を抱いたり、トラブルに発展したりすることのないように、あらかじめ利用目的とその必要性を明らかにし、本人の承諾を得ることが重要です。
また、情報の取り扱いについてもルールを策定し、関係者に周知しなければなりません。
健康情報などを取り扱う者に対しては、情報漏えいなどの防止措置を講ずるために、必要な教育及び研修を行い、労働者のプライバシーが守られた状態での情報交換が可能になるように、慎重に対応していくことが求められます。